多重行政、縦割り、タブー化でカオス状態
東京2020大会を控えた、2020年1月、日本で新型コロナの感染報告があった。
遂に、世界的感染拡大により2020年3月に、東京2020大会の1年延期が決定した。新型コロナは未知の疫病であり、何が対応策の正解か分からず、対応は過剰になったり、手付かずになったりと混乱した。
もともと、東京は超多重行政によって、責任と権限があいまいな部分がある。
内閣、省庁、都、区市町村、国の外郭団体、都の外郭団体、業界団体の本部や支部、人材の派閥などが重層化しており、実は、指示系統が1つではない。
そこに加えて、縦割りによって横断的な対応が阻害されていた。新型コロナウイルス対応の中心は福祉保健局(当時名称)だったが、幼稚園は生活文化局(当時名称)、公立小中学校は教育庁、小笠原など離島航路の船舶は総務局、経済活動は産業労働局などに別れており、局ごとの調整が必要であったし、福祉保健局以外の組織からは福祉保健局への遠慮が滲み出ていた。
とは言え、官僚組織の良い点も発揮された。批判されがちな「縦割り」だが、予防接種の全国的な展開は縦割りのなせる業だったと思う。ただし、医療行政への信頼を得るには予防接種の検証が必要だと思う。
「平時の体制」と「緊急時の体制」は別モノ
東京都の各局間に、縦割りの壁は厳然として存在するが、それでも平時は機能している。しかし、緊急時には、平時とは別の体制で動かす必要がある。
2024年11月に発足した石破内閣は、防災省の設置を掲げている。これは理にかなった政策であり、地震など自然災害の対応は気象庁、防衛省、国交省、地域の警察や消防などに別れているが、これらの機能を防災省に統合するならば画期的な政策だと思う。
東京都は、総務局内に総合防災部を設置し奮闘しているが、各局横断的な指揮は難しいだろう。いくら都職員が努力して「連携」しても組織が違えば指揮系統が異なり、調整や決裁に手間がかかる。条例等で緊急時の組織体制を決めておかないと、あいまいになり、全く機能しない。その間に事態は深刻化する。緊急時の都庁組織の見直しを早急に行う必要がある。
小池都知事が「東京大改革」から逃げられぬ公約にしたが…
小池都知事の二期目の選挙は、まさに新型コロナウイルスがまん延していた時期だった。都民ファーストの会に選対本部を設け、知事選公約等の作成にあたった。公約の原案が提示されたが、「東京大改革」の柱が無いことを指摘した。
この時、「都知事は改革から逃げるかも?」と感じた。
都知事が自民党大物国会議員や都議会自民党に接近している様子からも、最初に都知事に立候補した時とは変質していたことは、党内では周知の事実だった。
そこで公約案に加筆をした。「行財政改革・構造改革」として、都庁組織再編、外郭団体統廃合、中途採用比率拡大、広域自治体連携、二重三重行政の解消などを加えた。これらは都庁を解体する案ではなく、東京の力をより発揮できるようにするための政策として書き込んだ。都知事の二期目でこれらの公約に取り組んでいたら、都政は活性化したと思う。
案の定、これらの政策は、三期目の都知事選では排除されたので、よほど都合が悪い内容なのだろう。
医系技監制度への疑問
かつて、結核が流行した時、時の厚生省は臨床の第一線で活躍する医者に結核の対策を任せて成果を上げた。その後、厚生省の感染症部門は結核の治療法や予防法が確立すると、省内で花形の座を譲った。
現在、国や都の公務員のなかに医師の資格を持つ医系技監が存在している。彼らは公務員試験に合格しなくとも、医師資格があれば公務員試験を免除されている。新型コロナ対策を真剣に取り組むと、彼等の存在(壁)に突き当たる。
新型コロナ対応は、国も都も感染症の臨床経験がある医師が対応策を練るべきで、責任者になるべきだったのではないか?と疑問を感じている。医師の資格があろうとも、知識としての専門性だけでなく、臨床という経験値が揃うことで、はじめて国や都の医療政策を任せることができると思う。
厚労省内にも、都庁内にも、医系技監制度への疑問がある。波風を恐れてタブーにせず、制度を改め、次に来る未知の感染症に備えるべきである。優先順位は、都民の命が一番だ。
新型コロナ対応の検証がない
コロナ禍で困ったことは、情報が少ないこと、そして正しい情報の見極めが困難だった。この時ほど、情報が錯綜し、混乱したことはないと思う。
次も、また同じ組織体制で、また同じ発想で、また同じやり方で、また同じように混乱するのか。課題を明確にするために、タブーやウソの無い本当の検証が必要だ。
-1.jpg)
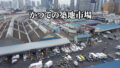

コメント